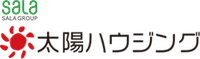太陽ハウジングの家づくりコラム
太陽ハウジングの家づくりコラム

- TOP>
- 家づくりコラム
2025.04.24
地鎮祭やる?やらない?後悔しないための判断ポイントとは?
こんにちは、太陽ハウジングです。
注文住宅を建てるときに、必ずと言っていいほど話題になるのが「地鎮祭(じちんさい)」。昔から行われてきた儀式ですが、最近では「本当に必要?」という声も増え、実施するかどうか迷う方も多くなってきました。
実際、地鎮祭を行う人と行わない人の割合は太陽ハウジングで半々くらいで、建築会社の方針や、施主の世代・価値観によっても選択が分かれています。
今回は、地鎮祭の意味や目的、実施のメリットと注意点、費用や流れなどをご紹介します。
実情だけでなく、「やった方がいい」と言える理由についても深く掘り下げていきますので、注文住宅をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

■地鎮祭の本来の意味と目的
地鎮祭とは、工事の始まりに際して土地の神様に建築の許しを得て、工事の安全とその土地に住む家族の繁栄を祈願する儀式です。通常は神主さんを招いて神式で行いますが、仏式やキリスト教式で行われることもあります。
一般的な儀式では、しめ縄で囲った清浄な場に祭壇を設け、酒、塩、米、水、魚、野菜、果物などの供え物を捧げて祝詞(のりと)を奏上し、施主や施工者が「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」を行い、工事の無事と家族の安寧を祈ります。
こうした儀式に宗教的な意味合いを感じる方も多いかもしれませんが、実際には工事関係者・家族が一堂に会することで、家づくりのスタートを実感する大切な節目という意味合いが強いかもしれません。
■地鎮祭って今でもやるの?
2025年現在でも、地鎮祭は一定数の方が行っています。太陽ハウジングでも約半数の施主が地鎮祭を実施しています。
他の住宅会社では、地鎮祭を積極的に勧める会社もあれば、希望があれば対応するスタンスの会社もあり、割合には違いがあります。
また、40代以上の世代では「やって当然」と感じている方も多く、親世代の意見で実施を決めるケースも見られます。一方で、若い世代では「必要性を感じない」「費用を抑えたい」との理由から、地鎮祭を省略するケースも増えてきています。
とくに大型分譲地などで、まだ周囲に住人がいない場合には、地鎮祭や近隣挨拶を行わない選択をすることもあります。
■地鎮祭をやらなかったら問題がある?
地鎮祭は法律上の義務ではないため、やらなかったからといって技術的にも問題はなく、建築に支障が出ることはありません。ただし、やらなかったことが、後から心理的な引っかかりになるケースもあるようです。
たとえば、
・親や近所の方から「地鎮祭やらなかったの?」と言われる
・工事中にトラブルがあったとき「地鎮祭をしなかったせい?」と思ってしまう
…といった“気まずさ”や“不安”につながることも。
■地鎮祭のスタイルも多様化
近年では、地鎮祭そのものを簡略化するケースも増えています。
たとえば、
・神主を招かず、施主だけで塩や酒をまいてお清めだけを行う
・テントや祭壇を設置せず、簡易な式にする
…といった簡略スタイルの地鎮祭も増えています。
柔軟な対応が可能なケースも多いため、「費用や準備が心配…」という方は、相談してみると良いかもしれません。
■儀式の流れと準備
一般的な神式の流れは以下の通りです。
開式の辞 一同拝礼
修祓(しゅばつ)の儀:神様をお招きする前に、祭壇と参列者をお祓いし清める
降神(こうしん)の儀:神籬(ひもろぎ)に、その土地の神様や地域の氏神様を迎える
献饌(けんせん):神様に祭壇のお供え物を食べてもらう。酒や水の蓋を取る
祝詞奏上:神主が地鎮、工事の安全、お施主様の発展を祈る旨の祝詞を読み上げる
清祓(四方祓い):土地の四隅に塩・酒・水を撒き土地を清めお祓いする
地鎮の儀(鍬入れ):施主が鍬を入れ、施工者が鋤を入れる
玉串奉奠(たまぐしほうてん):神前に玉串を奉り、二礼二拍手一礼
撤饌(てっせん):祭壇のお供え物を下げるという意味で、酒や水の蓋を閉じる
昇神の儀:神籬(ひもろぎ)に降りてきた神様を元の御座所に送る
閉式の辞
直会:祭壇にお供えしたお神酒で乾杯します。
準備や段取りは神主が主導してくれるので、施主側は説明を受けて当日に臨めば問題ありません。

■地鎮祭の目安
地鎮祭にかかる費用は、地域や規模によって異なりますが、一般的には以下の通りです。
・玉串料:3〜5万円(神主への謝礼)
・お供え物:1〜2万円(米、酒、魚、果物など)
・テント・祭壇:5〜7万円(建築会社が用意することが多いです)
・御車代:5,000円〜1万円(神主や関係者の交通費)
建築会社によっては、玉串料以外の費用が建築費に含まれていたり、テントは施主が手配するケースもありますので、事前に確認すると安心です。
ちなみに、太陽ハウジングの場合は以下の通りです。
・初穂料(玉串料):2万円(お供え物込み)
・祭壇:無料(神主さんが組み立てます)
・テント:33,000円(税込)
・御車代:お気持ちだけで結構ですと、かなり良心的かもしれません。
■地鎮祭の服装について
地鎮祭に決まった服装はありませんが、「工事の安全を祈るおめでたい儀式」という点を意識し、清潔感のあるフォーマルな装いが望ましいとされています。ただし、平服でも構いません。
ただ、現地は土や砂利の上で行われることが多いため、動きやすい靴やスカートの丈にも注意しましょう。
■参列者は?
基本的には、①お施主さん(ご自身・ご家族) ②建築会社の営業・現場監督・設計担当者・責任者、大工などの工事関係者 ③ご両親など親族(希望に応じて)が参列することが多いです。
小さなお子さまがいる場合は、誰か子守役になってくれる方がいると安心ですね。
地鎮祭のあとは近隣挨拶に行くことも多いため、施主と営業や現場監督が一緒に訪問するのが一般的です。
■地鎮祭のあとに忘れずに…ご近所へのご挨拶
地鎮祭の後は、これから始まる工事に向けて、近隣の方々にご挨拶をするのが通例です。
・向こう三軒両隣
・工事車両の出入りがあるエリア
・自治会長・町内会長(地域によって)
挨拶すべき対象の一例です。地域の慣習や営業担当者のアドバイスを参考に、柔軟に対応しましょう。
粗品としては、1,000〜2,000円程度の日用品や菓子折りが人気です。
この挨拶まわりは、ご近所付き合いの第一歩としてとても大切な機会です。ぜひ営業や設計の担当者と一緒に行いましょう。
■それでも地鎮祭、やるべき?──「やる・やらない」ではなく、「どう向き合うか」
地鎮祭は絶対にやらなければいけないものではありません。
実際、最近では大型分譲地などでまだ近隣に住人がいない場合や、若いご夫婦のみで家づくりを進めているケースなどでは、実施しない選択をする人も増えています。
でも一方で、「やってよかった」「やらなかったことを少し後悔している」といった声も確かにあるのです。
だからこそ、地鎮祭をするかどうかの判断は、損得や形式ではなく、「自分たちの価値観」に基づいて決めることが大切です。
ここからは、あえて「やったほうが良い」と考える理由について、少しだけ説明したいと思います。
■地鎮祭とは「工事の安全を祈願する儀式」──でもそれだけではありません
一般的に地鎮祭は、神主さんを招き、土地にしめ縄を張った神聖な空間で、これから始まる工事の安全と家族の無事を祈願する儀式です。
米・塩・酒・水などを供え、祝詞を奏上し、土地の四隅に塩をまいて土地を清め、施主が鍬を入れて祈願する――それが神式の地鎮祭の基本形です。
また、日取りも「大安」「友引」「先勝」といった六曜に加え、「十二直」や「三隣亡(さんりんぼう)」といった建築にまつわる吉凶に配慮するのが一般的です。とくに「午の刻(11〜13時)」が好まれる地域こともあり、土地の習慣や文化も色濃く反映されます。
ただし、地鎮祭の本質は、ただの「安全祈願」にとどまりません。
地鎮祭は、人生の一大プロジェクトである住まいづくりに、「心の区切り」を与えてくれる特別な時間でもあるのです。

■儀式に込める「想い」
儀式とは、日常とは違う「特別な行為」です。
地鎮祭では、普段の生活では味わえない厳かな空気のなかで、家づくりに関わる人たちが一堂に会し、決意を新たにします。その時間が、思いのほか大きな意味を持つものです。
たとえば、地鎮祭で施主が玉串を捧げる場面。
榊の葉に想いを託して、深く頭を下げる――その行為のなかに、「無事に家が建ちますように」「家族がこの家で幸せに暮らせますように」といった、言葉にならない祈りが込められます。
神社の形式や作法にとらわれずとも、こうした祈りの気持ちを持って臨むことができれば、地鎮祭には大きな意義があります。
■家族の節目としての地鎮祭
結婚式や七五三と同じように、地鎮祭もまた「家族の節目」として、とても尊いイベントです。
たとえば、小さなお子さん親の真似をしてお辞儀をしたり、写真におさめられた家族の姿がのちに宝物になったり。
そのときは意味がわからなくても、子どもたちが大人になったときに「あのとき、みんなで家づくりを始めたんだな」と思い出す――そんな心の原風景になるかもしれません。
また、親御さんをご招待して一緒に地鎮祭を行えば、「うちの子がここに家を建てるんだな」と実感してもらえる、感慨深い時間にもなります。
おじいちゃん・おばあちゃんにとっても、孫の成長を祝いながら家族の門出を見届ける、嬉しい機会になるでしょう。
■ご近所との関係を築く場として
地鎮祭が終わったあとは、ご近所への挨拶も行うのが通例です。
とくに建て替えなどで以前から知っている住人がいる場合、事前の挨拶はとても重要です。
また、建て替えに限らず、地域や住民同士のつながりが強いエリアや、昔ながらの町並みが残るエリアでは、事前に地鎮祭を行い、ご挨拶まわりをすることで「若いご夫婦だけど、きちんとしているな」と好印象を持ってもらえることもあります。
新しい生活のはじまりを、地域との良好な関係でスタートさせるためにも、地鎮祭は有効な機会となるでしょう。そういった意味でも、地鎮祭は大きな役割を果たしてくれます。
宗教的な意味だけでなく、儀式そのものに込められた意味や時間の重みを感じていただけるのが、地鎮祭の魅力です。
なによりお伝えしたいのは――地鎮祭は、記憶に残る最高の家づくりの始まりになるということです。
子どものころ見たお父さんの真剣な表情や、お母さんがそっと手を添えた瞬間。
乾杯のお神酒の味を思い出す日が、きっと何十年後にもやってきます。
地鎮祭は、そんな「記憶の始まり」です。
家づくりが、思い出と祈りに包まれた素敵な第一歩になりますように。
地鎮祭という節目を、ぜひ前向きに考えてみてください。